※アイデア募集を締め切りました。たくさんのご応募を誠にありがとうございました※
日本を代表する食品企業8社の有志による食の共創コミュニティ「Food Up Island(フード・アップ・アイランド)」がサステナブルな食産業や、Z世代がファンになる食品企業に関するアイデア募集を開始しました。
■Food Up Islandについて
今回、2つの課題についてアイデア募集を行った「Food Up Island(フード・アップ・アイランド」とは?
食産業は、地球環境のことから、社会、労働、物流、エネルギーなど
様々なところに関わっていて、社会課題は幅広く満載です。
ライフスタイルが多様化し、その問題も複雑化している現在、
未来に向けて一個人でも一企業でもなく、
同じ課題を持つ業界の仲間と一緒に
力を合わせて取り組む必要があります。
そんな中、2019年に誕生したのが『Food Up Island』。
自分たちのワクワクを共有し、
食にまつわるワクワクを社会に提供し続けたいと考え、
現在、食品企業を中心とした8社が仲間となり、
互いの強みを教え合って学び合う
『食の共創コミュニティ』集団となりました。
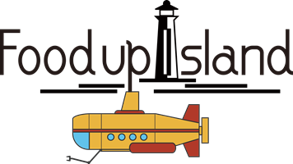

■アイデア募集の背景
「サステナブルな『食品』があったらぜひ欲しい!」
そんな消費者のニーズにお応えしたつもりで商品を製造してもいざ販売するとなかなか思うように売れない。
「なぜなんだろう?」
満足していただけるだけの価値が足りない?
価値の見せ方が違う?
何をどのように知れば買っていただける?
それともまだまだニーズが少ない?
値段が高いと買っていただけない?
食品企業にはこのような共通の課題感があります。
さかのぼること、高度経済成長期の日本において、美味しくて値段の安いものがたくさん提供されてきたことで、国民は飢えから解放され、多くの人が豊かな生活を送れるようになりました。
その一方で、「安いものが売れる」「もっと安く」という、いわゆる価格優先のバリューチェーンが出来上がったと言われています。
「安くて美味しい」が当たり前。そうでなければ、生活者(消費者)は買う気が起こらない。するとどうなっていくでしょうか。最悪の場合、デフレに繋がる可能性も否めません。
昨今、食の問題はとても大きく、地球環境への取組も急がれていますが、いわゆる価格優先がベースにある限り、生産者もメーカーも物流業者も小売業者も、食産業全体が疲弊しかねません。
そこでFood Up Islandは、
生活者(消費者)が求める真の価値を理解すると同時に、
食品企業の実情をきちんとお伝えして、
生活者の皆さんと一緒に考えながら、
サステナブルな『食産業』や、
新しい消費社会を皆さんと共に創っていきたいと考え
Idea Meetsに参加しました。
イノベーション・アイデアの募集に際し、イノベーション・パートナーである『Food Up Island(フード・アップ・アイランド)』(以下、FUI)の皆さんに、食品業界が置かれている状況や、アイデア募集に対する想いなどについて、インタビューを行いました。
【インタビューに答えてくださったFUIの皆さん】
FUI事務局:株式会社SEE THE SUN代表 金丸美樹さん
FUIメンバー(食品企業で実際に商品開発の研究員やマーケティングに従事している方々):5名
【インタビュアー】
若者アンバサダー:井上寛人、伊藤正人、大園鉄平、阪田留奈、三浦秀樹
DO!NUTS TOKYO事務局:梅原由美子
Food Up Islandについて
アイデア募集の背景
【インタビュー目次】
1. Food Up Island設立の経緯
2. FUIの活動と魅力
2.1 【活動のスタンス】
2.2 【競合他社がいるメリット】
3. FUIが抱える課題について
3.1 【サステナブルな商品を作る上での課題・難しさ】
3.2 【消費者に理解してほしいこと】
3.3 【サステナブルな商品を販売するということ】
3.4 【ヴィーガン市場について】
3.5 【FUIの取組のアピールについて】


1. Food Up Island設立の経緯
.jpg)
井上(アンバサダー):FUIさんは、競合他社の方が集まっている印象がありますが、企業さんが集まって1つの団体を作ろうと思うに至るまでにはどんなストーリーとかドラマがあったのかお聞きできればと思います。
金丸(FUI事務局):FUIは、2019年にできたのですが、その頃、私は新規事業をやっていて、様々な企業さんと情報交換をしていました。その中で、同じ食品メーカー同士、文化が同じなら悩みも同じだということに気づき、同じ課題を持ったもの同士が集まって国際連合のように「食品連合」みたいなものを作って一緒に何かできないか、というところから自然発生的にできた団体です。なので、募集をかけたというよりは、口コミで徐々にメンバーが増えていったような。その共通の課題を、みんなで解決しようという風になりました。
.jpg)
.jpg)
井上(アンバサダー):なるほど、腹落ちしました。そういうお互いの課題感が一致しているから一緒に変えて行こうよ、という前向きな流れだったわけですね。
金丸(FUI事務局):課題に対して1社では解決できないことに気づき、確かにこれはみんなで変えないと無理かもね、サステナブルな取組みたいなものも、1社だけやっていてもダメだから、みんなで変えて行こうよということを潜在的にみんな想っていたと思います。
.jpg)
.jpg)
井上(アンバサダー):1社でやっていこうとするとき、社内の上層部の方とのコミュニケーションが上手く合わないようなところもあるのでしょうか?
金丸(FUI事務局):役割が違うというか。別の業界ですが「社長は今の業績をあげることに注力し、会長は未来を見ている」という企業の話を聞いたことがあります。本当は両方やらなきゃいけないのですが、それぞれの立場での優先順位がありますし、事業活動をやって毎年ステイクホルダーに報告をしている以上、短期的な結果にフォーカスして動くことも多いです。ただ、一方で、サステナブルな取り組みなどを考えた際には、長期的な視点を持って、仲間とともに勉強しながら取り組む必要があると感じて有志活動が生まれました。
.jpg)
.jpg)
梅原(DO!NUTS TOKYO事務局):ライバル企業同士でお互いにすごく秘密主義なんじゃないかっていうイメージがありましたが、そういうところの垣根を取っ払ってというか、もともとコミュニケーションがあった中から、同じような事を見据えてやっていこうというわけですね。
金丸(FUI事務局):全てを開けっ広げにしているわけではないのですが、全部を隠す必要もなくて、一緒にやっていった方が良いことは、手を組んでやっていかなきゃいけないだろうな、という考えがみんなあって集まっています。
.jpg)
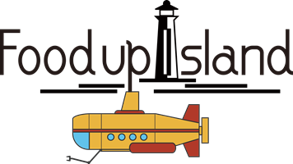
2.FUIの活動と魅力
2.1【活動のスタンス】
.jpg)
梅原(DO!NUTS TOKYO事務局):では、今回DO!NUTS TOKYOにご参加頂いた中での課題感を改めて伺っていきたいと思います。
.jpg)
大園(アンバサダー):まずFUIの団体としての一番大きなビジョンについてお聞きしたいです。どこを目指しているか、など。
金丸(FUI事務局):今FUIは3年目になります。数値的目標を持って取り組んでいるわけではなく、自分たちのスタイルとして、これからの食産業の課題にみんなで取り組んでいこう、というものがあります。社会課題に対してプロジェクトベースで動いており、会社のように、今年の目標はこれだ!と決めているわけではありません。みんなに共通して、根底に流れているのは「食を通してみなさんに笑顔を提供したい」、「自分たちもワクワクしながら、みなさんにもそのワクワクを伝えたい」という想いです。そしてその時の社会課題にみんなで取り組んでいく。また、企業の中にいるけど、FUIの中では「個を活かす」、 自分がやりたい課題に対して仲間を集めて解決しよう!というものです。
.jpg)
.jpg)
大園(アンバサダー):今プロジェクトは具体的にいくつありますか?
金丸(FUI事務局):私たちはプロジェクトのことを「分科会」と呼んでいますが、分科会としては3~4つが動いています。この分科会の進め方も会社のようにガチガチではなく、個人のモチベーションとペースに合わせて進めています。
.jpg)
.jpg)
大園(アンバサダー):仕事の中で組織としてやっているとイメージしていました。逆に組織立っていないことや、利益を追及していないことによるデメリットはありますか?
金丸(FUI事務局):皆さんそれぞれ所属する会社には承認を取って参加しているものの、あくまでも個人が自分のやりたいことを実現する場であり、良い意味で組織立っているわけではなく、フラットな場です。
頓挫したり消滅するプロジェクトもありますが、無理をして続ける必要もないと思っています。複数のプロジェクトに関わっている方や1つに集中している方など様々です。業務外でやりながら、うまく会社を巻き込んでいる方がいたり、なかなか今までに無いやり方で面白いのではと思っています。
メンバーには、研究員の方も多く、FUIで視野を広げることによって自身の研究に返ってくることもあり、そこで見つけた種をどこかで大きくする、という活用をしていらっしゃる方もいます。業務で研究中の商品やブランドに素晴らしい技術を活かすということもあります。
.jpg)
.jpg)
梅原(DO!NUTS TOKYO事務局):すごくユニークな取組ですね。食品企業単体で考えていたところよりも、FUIで視野が広がったことで、DO!NUTS TOKYOにもご参加いただけたということでしょうか。
金丸(FUI事務局):各メーカーには、サステナブル担当の部署がありますが、大きな企業の場合は、その部署だけが担当することになりがちです。ただ、サステナブル担当ではなく、開発にいる方も一人一人よく考えている。また、本当はその部署だけがやることではありませんし、開発側としてもサステナブル的な視点を持ちたいという方が多かったこともあり、FUIの中にプロジェクトができ、今回DO!NUTS TOKYOに参加しました。
.jpg)

2.2【競合他社がいるメリット】
-150x150.jpg)
伊藤(アンバサダー):「食品業界に関連するプロボノ活動の場」のようなことだなと思ったんですが、今どれくらいの人がメンバーとして参加されていますか?
金丸(FUI事務局):今年は23名のメンバーがいます。OBやメンターを含めると38名です。メンバー募集の方法は会社によりけりで、皆さんにお任せしています。
.jpg)
-150x150.jpg)
伊藤(アンバサダー):個人ベースでやっている活動だと思いますが、FUIという場があることのメリットは何でしょうか?
Sさん(FUI参加企業メンバー):何が面白いかというと、研究者の人材育成ができることだと思っています。バリバリの研究者の場合、研究を深く掘り下げているがゆえに、視野が狭くなったり、自社のマーケティングのことを知らなかったり、良いアイデアあるのに外に出していけなかったりすることがあります。
そんな中で、FUIでイベントを企画して商品を出してみたり、自分たちのアイデアをアウトプットすることをしてきました。この取組を続けてきたことで、若手の研究者同士の口コミを通じて広がりの輪ができてきています。

-150x150.jpg)
伊藤(アンバサダー):人材育成の観点、社会にも自分たちの組織にも良い、さらに個々人の機会にもなるという観点ですね。
金丸(FUI事務局):人材育成が目的の会社もあれば、そうでない会社もあります。参加目的も決めていません。何かここにある!と思う方が集まっています。
.jpg)
Wさん(FUI参加企業メンバー):他社とコラボできる場というのが大きなメリットです。自社でも色々な技術を持っていますが、自社だけでは限界があります。
自社内ではオープンイノベーションを進めようという動きが活発であり、色々な技術を持った他社さんがいることがすごく魅力的で、他社さんの技術ってどんなだろう、自分たちの技術に他社の技術や副産物を掛け合わせることで、もっと新しい何かを生み出せるのではないか、とワクワクしています。

Hさん(FUI参加企業メンバー):Wさんと同じで、他社さんの技術で遊べるところが「FUI最高!」と思っている点です。FUIには比較的大手と言われている企業が集まっていますが、皆100年くらいかけて積み上げてきた「技術」があります。
その「技術」を作り上げるには各社莫大な時間とコストをかけていますが、FUIで他社と協創することで、他の会社の100年分の技術も使える、こんな美味しいことはないと思っています。
例えば、森永製菓の商品に「甘酒」がありますが、甘酒という常温の飲み物をキリンの技術で氷点下の飲み物にしてみよう、という遊び方ができました。温度帯を変えるだけでも見せ方、味わい、シーンが大きく変わってきます。1社の技術を、菓子の領域、食品の領域、飲料の領域と自社の領域を超えて展開でき、市場も技術も掛け算で無限大になることがFUIの魅力だと感じています。

-150x150.jpg)
伊藤(アンバサダー):その一緒に作った商品の利益はどこに行くのでしょうか?
Hさん(FUI参加企業メンバー):それは検討段階でもあります。私たちは企業の壁がかなり薄くなった状態で集まっている団体ということもあり、どこかが儲けるということではなく、みんなで使える一つの共通のコンセプトを立てて、そのコンセプトにぶらさがるような商品をそれぞれの会社が作って、世の中に提案していくことができないかと考えます。
1社ではなく複数社でメッセージを伝えることで、世の中へのインパクトも大きくなると思います。各社それぞれが自立してモノづくりができるので、自社の作った商品で利益を出していくシステムというのが個人的には現実的かなと思っています。

-150x150.jpg)
伊藤(アンバサダー):プロモーションは一緒にやって、それぞれで作る、ということでしょうか?
金丸(FUI事務局):プロモーションというよりは、コンセプトの共有、社会変容を一緒にするチームとして考えています。今回のDO!NUTS TOKYOへの参加もそのような活動の一環と思っています。
.jpg)
-150x150.jpg)
梅原(アンバサダー):FUIの皆さんが本当に楽しそうに参加されていますよね。技術だけではなく、社会変革につながるようなイノベーションは、こういうワクワク感から生まれてくるのかなと感じました。DO!NUTS TOKYOも、ぜひそういう場にしていきたいと思います。
【2ページ目の目次】
3. FUIが抱える課題について
3.1 【サステナブルな商品を作る上での課題・難しさ】
3.2 【消費者に理解してほしいこと】
3.3 【サステナブルな商品を販売するということ】
【3ページ目の目次】
3. FUIが抱える課題について
3.4 【ヴィーガン市場について】
3.5 【FUIの取組のアピールについて】