若者アンバサダープログラムの一環として、学びシリーズがスタートしました!
こちらの「学びシリーズ」は、DO!NUTS TOKYO公式アンバサダーの皆さんに向けて行われるレクチャーであり、若者アンバサダーとして活動を行っていただく上で参考になると思われる知識の習得や、ご自身の考えをより深めていただくことを目的としています。
第1回目の今回は、2021年4月2日(金)に、DO!NUTS TOKYOの運営を行うサステナブルライフスタイルTOKYO実行委員会 委員長であり、株式会社三菱総合研究所 理事長の小宮山宏氏を講師にお迎えし、「持続可能社会ってどんな社会?」をテーマに開催しました。
レクチャー後は振り返りとして、グループディスカッションを行い、活発な意見交換が行われました。
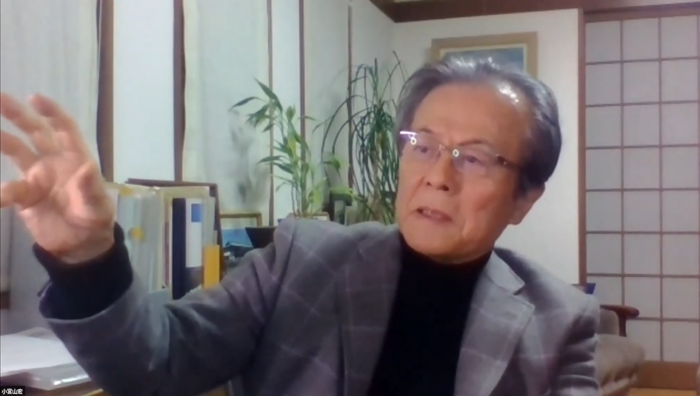
■レクチャーレポート
1. ポイント
- 今、人類史の転換期である。
- 地球が持続し、豊かで、人の自己実現を可能にする「プラチナ社会」を実現しなければならない。
- ゼロエミッション実現の方法は2つあり、二酸化炭素発生を抑制することと、二酸化炭素を固定することだ。
- 先進国の人口・人工物・物質はすでに飽和している。
- 2050年には、地球全体が飽和し循環可能な社会が来る。
- 資源の循環に必要なエネルギーは、低コストの再生可能エネルギーを利用できる。
- プラチナ社会に向けて、日本には課題とチャンスがある。
- 若者が中核となり、変革を起こしていかなければならない。
2. サマリー
産業革命以降、より便利なものが地球に増えて行く反面、二酸化炭素の増加や、自然環境の破壊が進んでいます。これらの被害を止めるためには、私たちの社会は「地球が持続し、豊かで、人の自己実現を可能にする社会」でなければなりません。この社会こそが、小宮山先生の提唱する「プラチナ社会」です。私たちは、今まさに、時代の転換期としてプラチナ社会を目指す必要があります。
プラチナ社会実現のためには、CO2排出量を限りなくゼロにすることを目指す「ゼロエミッション」の実現が欠かせません。ゼロエミッション実現の方法は、大きく分けて二つあります。CO2の発生を抑制する方法(省エネ、再エネ等)と、CO2を固定する方法(植林、緑化等)です。
ゼロエミッションや持続可能性を目指すうえで大切なキーワードが、飽和です。成熟した社会において、必要な人工物や物質の量は飽和します。事実、先進国の一人当たり自動車保有台数は、約0.5台/人で10年以上飽和しています。このような飽和した社会では、社会中の人工物を再利用すれば新たな人工物は必要ありません。そして、これは、先進国の話だけではありません。2050年をターゲットにした時には、地球全体で飽和することが見込まれ、地球全体で循環することも可能となります。
資源の循環には、エネルギーが欠かせません。例えば、日本には使用中ないしは使用済みの鉄(都市鉱山)がたくさんありますが、これらの再利用には電力が必要です。資源の再利用のためのエネルギーには、再生可能エネルギーが利用できます。再生可能エネルギーは、主に太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱などがあり、地域によって有利なものを選択できます。再生可能エネルギーは、化石燃料由来の電力と比較して発電コストでも優位に立ってきているため、経済合理性も見込めます。
このような社会を考えたとき、日本には大きな課題とチャンスがあります。たとえば、海外から化石燃料を輸入するのではなく、エネルギーを自給する「自給国家」を目指すことが可能です。他にも、放置された山林の林業を近代化・大規模化することで、輸出産業となり得ます。地域の活性化にもつながり、7%のCO2を固定化できるとされています。
今後、プラチナ社会を実現するためには、新しい取り組みや学びの場が重要です。例えば、ドイツのバイエルン州では、地域通貨を高校生が提案し、地域活性化に貢献した前例もあります。社会の転換期では、常に若者の力が求められます。自由で多様性のある考えをもとに、全員が同じ課題を背負うことで、一つの目標に向かって一緒に進んでいってほしいと考えています。
3. 感想
私たちは、普段どれだけ「社会」や「地球」という言葉を使っているでしょうか。少なくとも私は、今まで、普通に生活する中でこれらの言葉はほとんど発していません。そして、言葉を発していないということは、「社会」や「地球」を対象としてしっかり認識していなかったように思います。小宮山先生の講義の中では、当たり前のようにこれらの言葉が用いられていました。ゼロエミッションの解決を考えたときには、私は大きく視野を広げないといけないようです。
特に「飽和」は、まさにキーワードだと感じます。個人個人の欲望には際限がなさそうでも、社会的には物質の量が充足する事実。これは、ほとんどの人の感覚と異なる部分ではないでしょうか。私たちの世代は、人類史で初めて、飽和に向かう世の中で生きる世代です。この感覚を持つだけで、新しい考え方や発想を生み出すことができると思っています。
一つ、講義の内容とは違う考えを持った部分も存在します。輸出や輸入など、日本と他国の枠組みで議論が進んでいる部分がありましたが、ゼロエミッションを考えたとき、国境は関係ないと思っています。政治的・経済的要素を抜きにすると、日本国内でCO2を固定することと、国外でCO2を固定することは、地球レベルでは同一です。世界には、大きな課題とチャンスがあり、各国がそれに向けて努力することは重要だと思います。しかし、同じパイの中で日本が他国に「勝つ」というモチベーションには、少ししっくりきませんでした。地球規模の枠組みの問題だからこそ、できる限り「地球人」として思考の土台に立つ必要があると思っています。
この講義で最後に伝えられた「学び」の重要性は、まさに今私が感じていることです。何かの知識を得たり物事を認識したりすることで、新しい発想や、自分ならではの考え方を生むことができます。プラチナ社会の講義を通じた学びを自分の中でさらに進化させ、自分と同じ世代、下の世代にも伝えていきたいと思っています。
私は、2050年の自分を想像できません。しかし、2050年の地球はもっと想像ができません。視野を広げ、想像し、自分の力で変革を起こせるように、この「DO!NUTS TOKYO」でたくさんの仲間と学んでいきたいと思っています。
4. 同世代に伝えたい点
- この文章を読んでいる人こそが、第一に行動し、自分の周りに影響を広げられる人だと思っています。
- 社会に、地球に、視野を広げる必要があります。
- 正しい知識を得るためにも、新しい発想を得るためにも、重要なことは「学び」です。
- 私たちにとって、2050年は「未来」ではなく「将来」です。
- 一人ではできません。私たちみんなでこのチャンスを掴みにいきましょう。

【講師】
小宮山宏
サステナブルライフスタイルTOKYO実行委員会委員長
株式会社三菱総合研究所理事長
プラチナ構想ネットワーク会長
東京大学工学部卒業、同大学院工学系研究科修士課程・博士課程修了。2005年4月から2009年3月まで第28代東京大学総長を務める。サステナブルで希望ある未来社会を築くため、低炭素社会への取り組みやさまざまなプロジェクトを推進している。

【レポート執筆】
松井大輔/第1期若者アンバサダー
株式会社ゼロック 代表取締役
東京大学醍醐研究室で4年間産業エコロジーを研究。大学院卒業後環境分野の課題解決のための会社を設立し代表取締役に就任。現在は家庭向け太陽光発電の販売と、LCAによる環境コンサルティング事業を行っている。
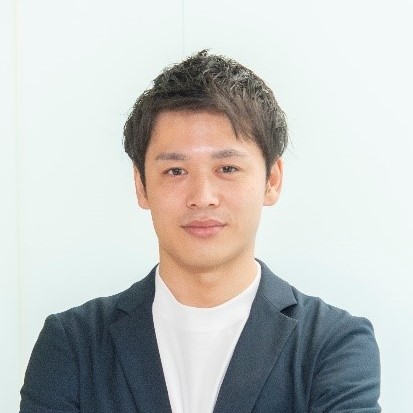
【レポート執筆】
三浦秀樹/第1期若者アンバサダー
株式会社ゼロック 取締役
青山学院大学経済学部卒業後、株式会社あおぞら銀行に入行。名古屋支店にて個人資産運用業務を経験した後、本店個人営業本部にて営業企画・運営に従事。2019年9月、小学校時代からの友人である代表の松井と株式会社ダブルボランチ(現:株式会社ゼロック)を設立。
【関連記事】学びシリーズ第2回「ゼロエミッション東京戦略」
【関連記事】学びシリーズ第3回「気候変動と土地利用」
【関連記事】学びシリーズ第4回「有機農業が育む生物多様性と地域資源活用」
【関連記事】学びシリーズ第5回「生活者を巻き込む森づくり」
【関連記事】学びシリーズ第6回「家では何ができるか?そのリアリティ」
【関連記事】学びシリーズ第7回「あなたの1円が社会や未来を変える!?」
【関連記事】学びシリーズ第8回「SDGsを活かした地域づくり」
【関連記事】学びシリーズ第9回「みんな参加型の循環型社会」
【関連記事】学びシリーズ第10回「水産資源の現状とMSC認証制度について」
【関連記事】学びシリーズ第11回「地域でSDGs・ゼロカーボンを実践し、世界につながる」
【関連記事】学びシリーズ第12回「葛西臨海公園 生態系観察会」


