若者アンバサダープログラムの学びシリーズ第3回目、今回はレクチャー動画と若者アンバサダーによるレポートをお届けします。
「学びシリーズ」は、DO!NUTS TOKYO公式アンバサダーの皆さんに向けて行われるレクチャーであり、若者アンバサダーとして活動を行っていただく上で参考になると思われる知識の習得や、ご自身の考えをより深めていただくことを目的としています。
第3回目は、2021年7月2日(金)に、DO!NUTS TOKYOのアドバイザーであり、公益財団法人地球環境戦略研究機関 (IGES) 生物多様性と森林領域 上席研究員の山ノ下麻木乃氏を講師にお迎えし、「気候変動と土地利用」をテーマに開催しました。
レクチャー後は振り返りとして、グループディスカッションを行い、活発な意見交換が行われました。
■レクチャー動画
■レクチャーレポート
1.ポイント
- 森林は気候変動の解決において大切な存在。
- 森林の吸収機能は唯一確立された自然のテクノロジー。
- 農林業は大きな排出源でもある。
- 日本にも世界の森林減少に責任がある。
- 社会システムを変える。
2.サマリー
森林は、木材の生産だけでなく多様な生物の住みかや地球温暖化の原因である二酸化炭素を吸収するなどたくさんの役割を持っている大切な存在です。これらの森林の役割の大切さを私たちは忘れてはいけません。今回は気候変動と森林の関係に関してお話を伺いました。
地球温暖化の防止において、森林は欠かせない存在です。私たちが排出した二酸化炭素を吸収してくれます。現在、CCSという二酸化炭素貯留の技術開発が進められていますが、今すぐ吸収することができるのは森林しかありません。また、鉄を使って家を建てるよりも木を使う方が二酸化炭素排出量は抑えられます。このように森林は気候変動だけに注目しても様々な役割をおり、大切に扱うべき存在です。
今まで人間は農業や家畜において多くの土地を使っていますが、近年の人口増加に伴い、森林を農地に変えることで生産量を保ってきました。さらに、動物性食品は植物性食品に比べ効率が悪いにもかかわらず、食生活は動物性食品中心に変化しました。これまでのやり方で食糧生産は続いていいのでしょうか。
これから農林業分野では温室効果ガスの大幅な削減が求められます。そのためには、森林の減少を防ぎ植林などにより森林面積の拡大をし吸収力を上げる必要があります。壮大で身近に感じられない人が大半だと思います。実は森林は食卓とも繋がっています。食料システムからの排出は世界全体の約30%にあたります。直接農林業に関わることはなくても、食品ロスをなくしたり輸送や加工に伴う排出を減らすことで森林の減少を防ぎ、温室効果ガスの排出を減らすことができます。
もう一つ、森林と気候変動の関係を考えるうえで重要なことがあります。それは日本の食料が海外に依存していることです。日本の牛肉の食料自給率は11%と低い状況です。何気なく毎日食べている食材は、遠い国の森林を破壊して作られた農地で生産されているのです。たとえば、パーム油の問題を紹介します。私たちが普段食べているポテトチップスなどの食べ物や洗剤にはパーム油が含まれています。パーム油は液体、固体で使用できる万能な油ですが、マレーシアやインドネシアの熱帯雨林減少の原因になっています。一方、日本は森林減少がほぼ起こっていません。それは森林を守っているのではなく、海外から食料を輸入しているからです。このように、日本には海外で森林破壊を起こしている国としての責任があります。
最近、ビーガンやフレキシタリアンといったサステイナブルな食生活を送る人が増えています。気候変動の解決において消費者の選択は重要です。肉の消費量を減らしたり、認証製品を選んだりすることで温室効果ガスの削減につながります。
しかし、これだけでは本質的な解決にはつながりません。日本人全員が菜食になっても、排出削減量は微量です。1人が変化することは無意味ではないですが、十分とは言えません。
消費者だけではなく企業や行政と連携して取り組んで、「社会システム」を変化させることが必要です。
3.感想
環境問題に取り組みたいと思ったとき、最も早く取り組めるのが食生活だと思います。その日から菜食にしたり環境に良い食材を選ぶことができます。
今回の講義で一番衝撃的だったのが、「個人の取り組みは無意味ではないが、十分とは言えない」という内容でした。たしかに、誰かが肉を食べなくなっても隣の家の人は食べているかもしれません。また、世界のどこかで森林破壊をしてまで私たちの食材を作っている人、国があります。社会システムを変えることが必要ということを心にとめていきたいと思います。
4.同世代に伝えたい点
- 森林は沢山の役割を持っている大切な存在。
- 森林は食卓と繋がっていて、動物性食品はたくさんの土地が必要。
- 海外からの輸入している食料が多い日本には、森林破壊への責任がある。
- 消費者だけでなく企業や行政と連携することが必要。
- 1人の変化は十分とは言えない。社会のシステムを変えることが必要。

【講師】
山ノ下麻木乃/DO!NUTS TOKYOアドバイザー
公益財団法人地球環境戦略研究機関 (IGES) 生物多様性と森林領域 上席研究員
森林と気候変動について研究を行っている。途上国農村部の地域住民を主体とした森林管理に興味があり、地球規模の気候変動対策と地域コミュニティのシナジーを模索している。
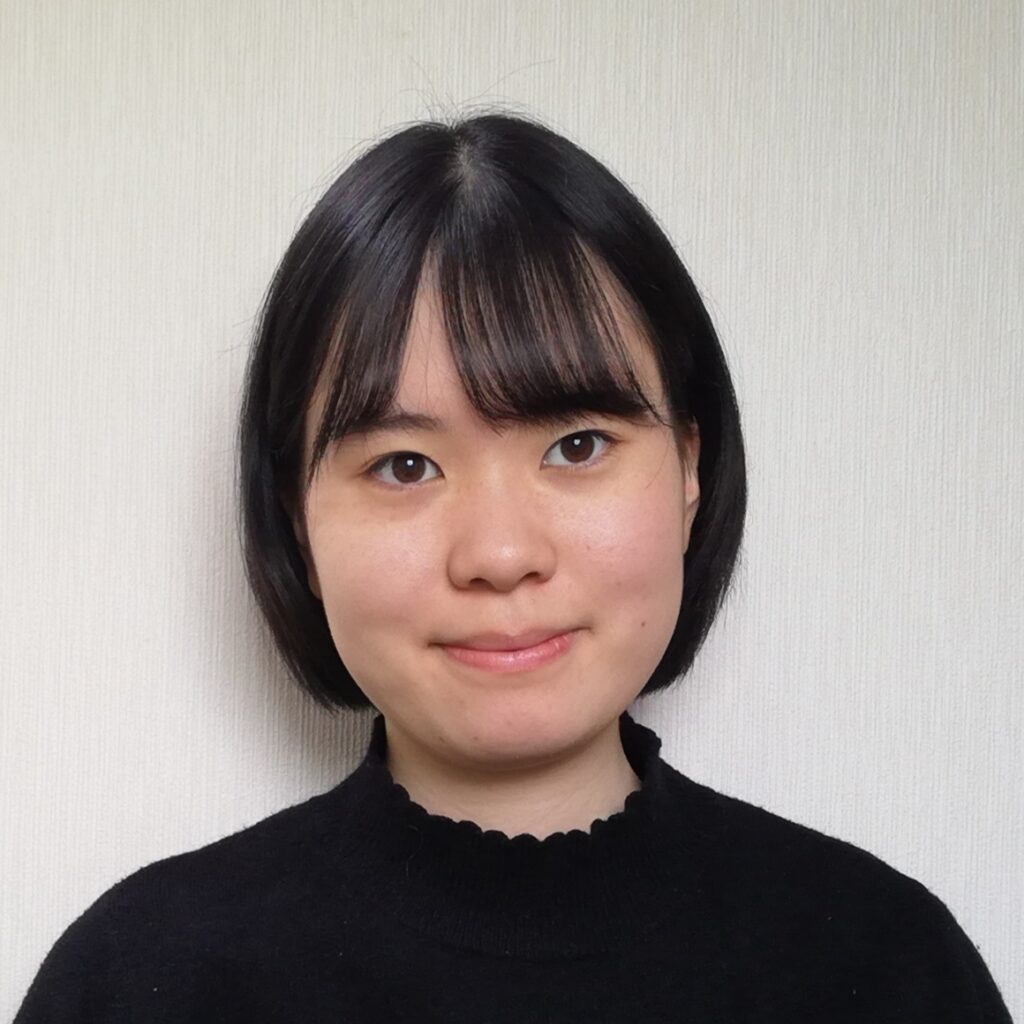
【レポート執筆】
阪田留菜/第1期若者アンバサダー
慶應義塾⼤学総合政策学部在学中。アンバサダー最年少の19歳。気候危機に対するムーブメント「Fridays for Future Tokyo/Japan」ではオーガナイザーとして活動中。
【関連記事】学びシリーズ第1回「持続可能社会ってどんな社会?」
【関連記事】学びシリーズ第2回「ゼロエミッション東京戦略」
【関連記事】学びシリーズ第4回「有機農業が育む生物多様性と地域資源活用」
【関連記事】学びシリーズ第5回「生活者を巻き込む森づくり」
【関連記事】学びシリーズ第6回「家では何ができるか?そのリアリティ」
【関連記事】学びシリーズ第7回「あなたの1円が社会や未来を変える!?」
【関連記事】学びシリーズ第8回「SDGsを活かした地域づくり」
【関連記事】学びシリーズ第9回「みんな参加型の循環型社会」
【関連記事】学びシリーズ第10回「水産資源の現状とMSC認証制度について」
【関連記事】学びシリーズ第11回「地域でSDGs・ゼロカーボンを実践し、世界につながる」
【関連記事】学びシリーズ第12回「葛西臨海公園 生態系観察会」


