若者アンバサダープログラムの学びシリーズ第9回目のレポートです。
「学びシリーズ」は、DO!NUTS TOKYO公式アンバサダーの皆さんに向けて行われるレクチャーであり、若者アンバサダーとして活動を行っていただく上で参考になると思われる知識の習得や、ご自身の考えをより深めていただくことを目的としています。
第9回目は、2021年9月24日(金)に、日本環境設計株式会社 取締役会長の岩元美智彦氏を講師にお迎えし、「みんな参加型の循環型社会」をテーマに開催しました。
レクチャー後は振り返りとして、グループディスカッションを行い、活発な意見交換が行われました。
■レクチャーレポート
1.ポイント
- これからのメーカーのあるべき姿は、一方通行ではなく、双方通行である
- 自分たちの便利な生活の裏側では、地下資源争奪戦争が起きている
- それを止めるには、消費者参加型の循環型社会である
- 循環型社会の中心は、企業や団体ではなく、消費者である
2.サマリー
循環型社会のキーワード①技術
ケミカル技術を使えば、製品から製品へのリサイクルが可能であり、その品質は約95%以上の再生率・バージン素材と同等である。また1回きりではなく、10回、100回以上何回でもリサイクル可能である。
ゴミから作った資源を『地上資源』を使い循環型社会を目指す。
資源環境では『炭素』がポイント。
キーワード②みんな参加型のリサイクルインフラを作る。
「買う・使う・捨てる」から「リサイクル・買う・使う」へシフトチェンジさせる。そのためにお店に回収ボックスを設置。(PLA-PLUSプロジェクト(外部リンク))
→無印良品・JINS・Starbucks・タカラトミー・学校・幼稚園・海外など
→2010年にわずか6社の参加でスタートしたリサイクルプロジェクトは現在累計にして150ブランド以上が参加
リサイクルを目的にリサイクルした服でバックトゥーザフューチャーイベントを開催し、2015年地上資源(服やおもちゃ)でデロリアン(バックトゥーザフューチャーに登場する車)を動かしたいと提案し、見事イベントを開催。大盛況。
→ハリウッド側は戦争やテロの本質的な要因となる地下資源解決を理由に許可
みんなでオリンピック・パラリンピックを作ろう
背景としては、平和の祭典なのに、戦争やテロに直接的・間接的に関係している地下資源を使わないようにするため。
①みんなで携帯電話を集めてメダルをつくろう
②バイオマス燃料で聖火を灯そう
③みんなで衣類を集めてユニフォームを作ろう
④みんなでTシャツを集めて飛行機を飛ばそう
その他にも、服をリサイクルした燃料で飛行機を飛ばそう(JALとのプロジェクト)や服から服を作ろうプロジェクト(one buy・one recycle・one peace)、G20海洋ゴミで商品を作るプロジェクトなどさまざまなプロジェクトを通して、循環型社会への貢献をしている。
我々の便利な生活の裏側には地下資源を奪い合う資源争奪戦争が起きている。その戦争を終わらせるには金でもなく武器でもなく、みんな参加型の循環型社会である。
3.感想
環境問題に取り組む企業が1番課題にしている「消費者にどうのようにして興味を持ってもらうか?」という部分がとてもうまく、時代のトレンド、消費者のニーズを上手く抑えている取り組みをしている企業で話を聞いていて、とてもワクワクしました。
また、社会問題の本質を捉えた問題解決をできる問題発見・問題解決能力が強みであり、それを支える世界最先端の技術がある日本企業を誇りに思いました。一度実際に工場を見学してみたいです!
4.同世代に伝えたい点
- 気候変動問題を解決するのは企業でも政府でもなく我々です。小さなところからでもいいので取り組む意義があります。
- 環境に配慮した製品を使ってみる、SNSで発信するなどできることはたくさんあります。
- この記事を読んでいただき、知識を入れることで生活の仕方や意識も少しずつ変わってくると思うので、知ることから始めるでも大歓迎です!一緒に気候変動について少しずつ学んでいきましょう!
【講師】
岩元美智彦 日本環境設計株式会社 取締役会長
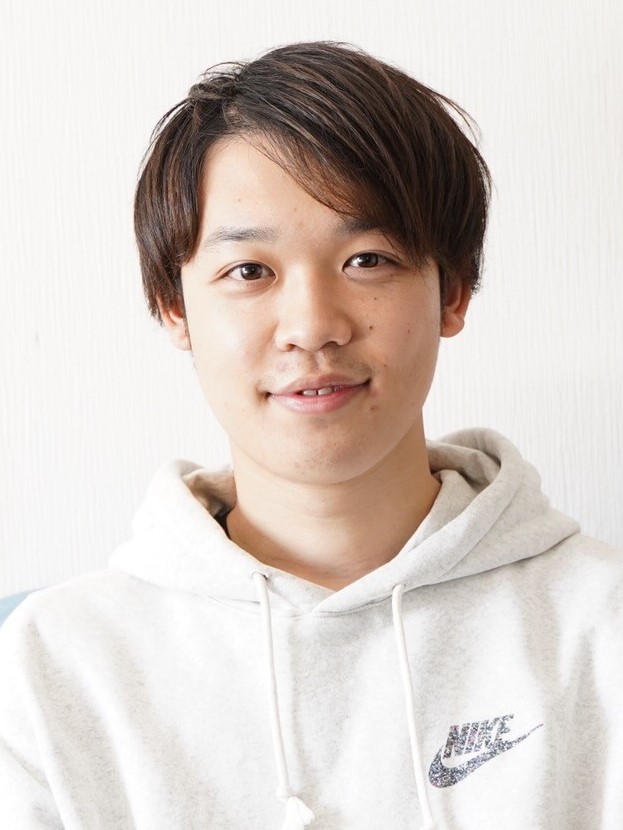
【執筆】
大園鉄平/第1期若者アンバサダー
ITのマーケティング事業をしながら副業にて「人々のウェルネスを最大化する情報の提供」をミッションに環境・ウェルネス系ブログ「For The HUWELL」を運営し、クリーンアップ活動や環境・SDGsに関する情報を発信。マーケター、クリエイター、環境活動家として活躍。
【関連記事】学びシリーズ第1回「持続可能社会ってどんな社会?」
【関連記事】学びシリーズ第2回「ゼロエミッション東京戦略」
【関連記事】学びシリーズ第3回「気候変動と土地利用」
【関連記事】学びシリーズ第4回「有機農業が育む生物多様性と地域資源活用」
【関連記事】学びシリーズ第5回「生活者を巻き込む森づくり」
【関連記事】学びシリーズ第6回「家では何ができるか?そのリアリティ」
【関連記事】学びシリーズ第7回「あなたの1円が社会や未来を変える!?」
【関連記事】学びシリーズ第8回「SDGsを活かした地域づくり」
【関連記事】学びシリーズ第10回「水産資源の現状とMSC認証制度について」
【関連記事】学びシリーズ第11回「地域でSDGs・ゼロカーボンを実践し、世界につながる」
【関連記事】学びシリーズ第12回「葛西臨海公園 生態系観察会」


