「学びシリーズ」は、DO!NUTS TOKYO公式アンバサダーの皆さんに向けて行われるレクチャーであり、若者アンバサダーとして活動を行っていただく上で参考になると思われる知識の習得や、ご自身の考えをより深めていただくことを目的としています。
第26回目は、2023年10月10日(火)に、特定非営利活動法人Gender Action Platform 理事の大崎麻子氏を講師にお迎えし、「ジェンダー平等について」をテーマに開催しました。
レクチャー後は振り返りとして、グループディスカッションを行い、活発な意見交換が行われました。
■レクチャーレポート
1.ポイント
- ジェンダー平等は国際社会の共通の目標である
- 日本でも身近な問題である
- 無償ケア労働(人のお世話にまつわる労働)は生産労働を補完する重要な労働である
- 自分で決める力をつけること(エンパワーメント)が重要
- ユースを中心にジェンダー平等に関するアドボカシーが行われて実際に政策に反映されている
2.サマリー
ジェンダー平等とは、男性と女性が等しく権利と機会を享受し、責任を分かち合い、意思決定にも対等に参画できる状態を指します。また、個人が性別を理由に直接的・間接的に差別されないようにすることです。
さらに、女性・女の子のエンパワーメントとは、人生や日常生活におけるあらゆる選択肢を自分の意志で選び取って生きていくための力をつけることです。「健康」「教育」「経済力」「参画(政治・社会)」の4つの「力」があります。
私たちは、家庭、学校、職場、メディアで見聞きしたり、経験したことから、様々な影響を受けますが、「男らしさ」「女らしさ」といった固定観念や性別役割分業意識もその過程で形成され、内面化されます。また、そうした性別役割分業意識が組織や社会・経済に構造化されています。「ジェンダー平等」が目指しているのは、こうした構造や社会規範を変革し、すべての人が性別にかかわらずに尊重され、責任を分かち合い、あらゆる選択ができる状態を作ることです。
なぜ世界がジェンダー平等を目指す必要があるかというと、3つの観点があげられます。1つ目は、国連憲章や世界人権宣言で述べられるように、ジェンダー平等は普遍的だからです。2つ目は、経済合理性に叶うためです。3つ目としては、SDGsをはじめとした目標にあるようにサステナビリティに不可欠だからです。さらに、SDGsでは、ゴール5として「ジェンダー平等」が掲げられていますが、それだけではなく、17のすべてのゴールにジェンダー視点を主流化しなければならないと強調しています。
少し具体的な例を見てみましょう。
SDGsでは、ゴール5のターゲット4として「無償ケア労働(人のお世話にまつわる労働)の再分配」が挙げられています。育児、介護、看護、家事、コミュニティでのサポートなどです。これらの無償ケア労働は、今まで女性の労働、女性の方が向いているとされていました。無報酬なので社会的・経済的価値が無いように見えますが、実はこうしたケア労働が、日々の経済活動・生産活動を下支えしています。また、育児は次世代の労働力を育むことでもありますから、人的資本の蓄積に直接的に寄与しています。価値の高い労働であり、時間も労力もかかる労働ですが、経済的な報酬はありません。重要な労働を担いながら、経済力を持たない女性と、報酬のある労働を担う男性との間には力関係が生まれます。また、途上国では、水汲みや薪集めなど時間も体力も使う労働もあり、それが女子教育、女性の経済・社会・政治参加の大きな障壁となっています。日本の現状としても、女性が男性の5.5倍無償ケア労働を行っているというデータもあり、それが女性のキャリア形成や経済・政治参画の大きな障壁になっています。
こういった社会の中で私たちは何をすればよいのでしょうか?社会は人々の選択の積み重ねでもあります。人々の選択の仕方が変われば、社会も変わります。まずは自分で決める力をつけることが重要であると大崎氏は言います。
例えば、就活。従来の評価軸では、偏差値、親・先生の指導、人気度、初任給、福利厚生などで決めていたかもしれません。しかし、新しい評価軸であるジェンダー平等やサステイナビリティといった軸をもつことで、社会は変化します。大崎氏は実際に企業を選ぶ際の指標を具体化した、「本気でサステナブルカンパニー」というプロジェクトを行っています。
さらに、日本の社会も、2022年以降、急速に「法律」「政策」が進展しているそうです。これらの背景としてはコロナの影響もありますが、若者の力もあると強調します。
実際に、第5次男女共同参画基本計画へのユースからの提言で、就活のセクハラや性の多様性(LGBTQ)、性教育に関する提言が行われ、計画へ取り入れられました。また、企業広告の男女の描かれ方に関しても、ユースへ調査が行われて、「ユースが考えるジェンダーに配慮した広告にするためのチェックリスト」が作成され、企業との対話に用いられました。このように活動を行い、社会変革をリードすることがこれからも求められます。
3.感想
企業などで、男女差別したつもりはなくても、データでみると男女で賃金や職務経験に差がでてきてしまうといったお話が印象的でした。世界で達成されるべき目標として、ひとりひとりのエンパワーメントが進み、社会が変わっていく必要があると思います。
また、ジェンダー平等に関するユースのアドボカシー活動が政策にかなり反映されているとのことで、気候変動分野でも、そのような活動を参考にアドボカシーを行っていきたいです。
4.同世代に伝えたい点
- 自分の生き方を「自分で決める」こと
- 自分で決めるための「評価軸」「基準」を持つこと
- 自分で決めるためのジェンダー平等、サステナビリティに関連した「情報」を集めること
- 変容を地域レベルで目指す。
- ユースとして提言を行うと政策として取り入れられる可能性があること

【講師】
大崎麻子/特定非営利活動法人Gender Action Platform理事
米国コロンビア大学国際公共政策大学院にて国際関係修士号(国際人権問題専攻)取得。国連開発計(UNDP)でジェンダー平等と女性のエンパワーメントを担当し、世界各地で女性の教育、雇用・起業、政治参加等のプロジェクトを手がけた。現在は、グローバル動向を熟知する専門家として、国際機関、政府機関、自治体、メディア、民間企業などで幅広く活動。内閣府「男女共同参画会議計画実行・監視専門調査会」委員、外務省「女性・平和・安全保障(WPS)国内行動計画」評価委員、関西学院大学総合政策学部客員教授等を務める。大学院在学中に長男を、国連在職中に長女を出産し、子連れ出張も多数経験。近著に「エンパワーメント 働くミレニアル女子が身につけたい力」(経済界)
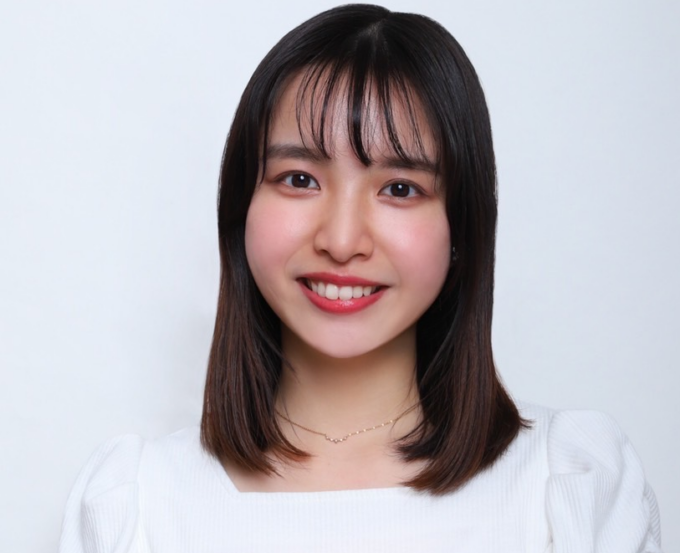
【レポート執筆】
柴 真緒/第3期若者アンバサダー
東京大学大学院で農学を学び、植物分子生物分野の研究を行う傍らおしゃれにSDGsを取り入れることをコンセプトとするメディア「cheer!SDGs」を運営にも力を入れている。
【関連記事】学びシリーズ第1回「持続可能社会ってどんな社会?」
【関連記事】学びシリーズ第2回「ゼロエミッション東京戦略」
【関連記事】学びシリーズ第3回「気候変動と土地利用」
【関連記事】学びシリーズ第4回「有機農業が育む生物多様性と地域資源活用」
【関連記事】学びシリーズ第5回「生活者を巻き込む森づくり」
【関連記事】学びシリーズ第6回「家では何ができるか?そのリアリティ」
【関連記事】学びシリーズ第7回「あなたの1円が社会や未来を変える!?」
【関連記事】学びシリーズ第8回「SDGsを活かした地域づくり」
【関連記事】学びシリーズ第9回「みんな参加型の循環型社会」
【関連記事】学びシリーズ第10回「水産資源の現状とMSC認証制度について」
【関連記事】学びシリーズ第11回「地域でSDGs・ゼロカーボンを実践し、世界につながる」


