「学びシリーズ」は、DO!NUTS TOKYO公式アンバサダーの皆さんに向けて行われるレクチャーであり、若者アンバサダーとして活動を行っていただく上で参考になると思われる知識の習得や、ご自身の考えをより深めていただくことを目的としています。
第32回目は、2024年1月30日(火)に、コミュニティエナジー株式会社代表取締役の南原 順氏を講師にお迎えし、「『地域にとっても価値ある再エネ』とは何か、をあなたはどう考えるか」をテーマに開催しました。
■レクチャーレポート
1.ポイント
- 大規模な再エネ導入に伴って地域では土砂崩れ、景観、騒音などのトラブルが発生し再エネ導入に反対する人もいることから、地域にとっても価値がある再エネを考えていかなければならない。
- 地方は多くの再エネ導入のポテンシャルを秘めている。
- 地域と促進側の間でのコミュニケーションが重要である。
2.サマリー
- COPなど国際的な取り決められ再エネを大量に導入していかなければならないが、それに伴って、地方に土砂崩れや景観への悪影響など被害が出てきているもしくはそれを懸念して反対しているところもある。
- 日本の地方には再エネの供給可能量が需要を上回り、地域外に販売できる地域が多くある。
- 再エネは地域の雇用創出や企業誘致の可能性を持っている。
- 災害や経済縮小などの地域特有の課題の解決手段になりえる。
- 再エネには初期コストの高さ、長期資金の調達やインフラ設備の導入など課題も多い。
- 再エネを導入したい側と地方の住民でコミュニケーション不全が起きている場合がある。
3.感想
- エネルギー問題や気候変動の解決を重要視する側と、電気は不足していない中で、地域の自然や生態系または周りの景観などを重要視する地方の方々どちらも大切な価値観だと思うし間違っていないと思いました。双方が信頼してお互いを尊重しながら対話を重ねてコミュニケーションを取り続けることが大切だと思いました。地域を含めたそれぞれの立場の人にとって価値のある再エネとは何かを考えていきたいと思いました。
4. 同世代に伝えたいこと
- 若者たちが率先して地方とのコミュニケーションを取り、懸け橋になっていく必要がある。
- 声が大きい人からの声だけでなく、普段スポットライトが当たりにくい人からの声やローカルからの声を拾っていく必要がある。
- 一つの事象を片方からだけで見ていくのではなく、複眼的に見ていく必要がある。
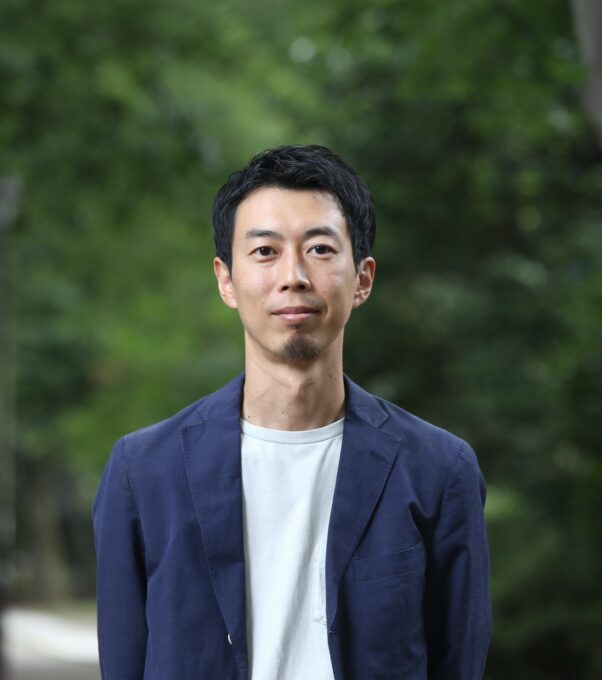
【講師】
南原 順/コミュニティエナジー株式会社 代表取締役
島根県浜田市生まれ
京都大学大学院地球環境学舎修了(修士・環境政策専攻)
2005年より南信州を中心に、市民が出資・参加する自然エネルギー事業の立ち上げ及び運営に携わる。その後、ドイツを拠点に欧州4カ国での太陽光発電プロジェクトの開発・運営を経験。帰国後は日本企業にて国内のメガソーラーの事業企画、開発を行う。2016年にコミュニティエナジー株式会社を設立し、島根県浜田市を拠点に地域主導の自然エネルギー導入の支援を行う。
現在
・浜田市脱炭素政策アドバイザー
・島根大学非常勤講師
・縁パワーしまね運営メンバー
・株式会社エネルギーラボ沖縄 フェロー(政策分野)

【レポート執筆】
渡邊透/第3期若者アンバサダー
大学のゼミでは惑星平和学を研究し、2023年秋からThe Chinese University of Hong Kongに1年間交換留学。サステナビリティと国際関係論を学ぶ。
【関連記事】学びシリーズ第1回「持続可能社会ってどんな社会?」
【関連記事】学びシリーズ第2回「ゼロエミッション東京戦略」
【関連記事】学びシリーズ第3回「気候変動と土地利用」
【関連記事】学びシリーズ第4回「有機農業が育む生物多様性と地域資源活用」
【関連記事】学びシリーズ第5回「生活者を巻き込む森づくり」
【関連記事】学びシリーズ第6回「家では何ができるか?そのリアリティ」
【関連記事】学びシリーズ第7回「あなたの1円が社会や未来を変える!?」
【関連記事】学びシリーズ第8回「SDGsを活かした地域づくり」
【関連記事】学びシリーズ第9回「みんな参加型の循環型社会」
【関連記事】学びシリーズ第10回「水産資源の現状とMSC認証制度について」
【関連記事】学びシリーズ第11回「地域でSDGs・ゼロカーボンを実践し、世界につながる」


